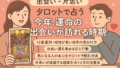昔、まだ世界に夜がなかった頃、
一柱の獣が月を喰らった。
その獣は神に近く、人に似ていた。
彼は夜を望んだのではなく、沈黙を与えるために月を呑んだ。
光を失った世界に、初めて咆哮という音が生まれた。
それが、「最初の咆哮者(ルウの始祖)」である。
血筋の宿命 ―「咆哮する者たちの系譜」
この血は、名前を持たない。
彼らは、名を失った魂に、名もなく寄り添う者たち。
誰にも呼ばれなかった魂を、
誰にも見えなかった痛みを、
彼らは咆哮だけで受け止め、送り出してきた。
代々、狼の右腕に毛皮を持つ者がその証を帯びる。
それは送れなかった魂の重さであり、
その右腕に棲みついた魂は、魂送りのパートナーになる。
ルウの特異性 ―「棺舟に乗れなかった唯一の者」
この血に連なる者は、
いずれ必ず自らも棺舟に乗り、
魂と共に向こう岸へ還る運命にある。
だが、ルウはその法則から逸れた。
自らが送り出されるべき魂でありながら、なお咆哮し続ける者。
自らの魂を送ってくれる者がいなかった唯一の者。
彼は、「月を喰らった血」のなかでも例外であり、
最も深く記憶に縛られた存在だった。
月を喰らった咆哮の血なのか?
月に食われた者なのか?
名なき魂を呼ぶために、
名を持たず生まれた者たちが狼男だった。
右腕に纏うは、喪われた過去。
言葉ではなく、叫びで呼び声に応える。
「ルウの右腕」の由来にまつわる物語断章
「狼の右腕に毛皮を持つ者」とは、送り損ねた魂が、ルウの内に
棲みついてしまったのである。
吸血鬼は、血統に依存するが、狼男の素晴らしさは、個人の資質に
依存する。
悲惨な死を迎えた魂に生や命を思い出させて、魑魅魍魎になった姿から
美しい姿に戻すのが狼男ルウである。
咆哮で12ハウスの月を太陽に変える。
ルウの右腕に棲む魂は、限りなく神に近い存在なのだ。
ルウ=自らが選ばれたのではなく、「選んだ」者
右腕の魂=神に近い魂を、なおこの世に留めている唯一の存在
月の光の中で、あの魂を見つけてしまった者。
その魂は、あまりに純粋で、あまりに悲惨で、
本来なら魑魅魍魎へと堕ちるはずだった。
だが、ルウはその魂を棺舟に乗せず、右腕に宿らせた。
その魂は、咆哮を聞くたびに命の記憶を取り戻し、
美しい姿に還ろうとしている。
この魂は誰か?
それは、太古の時代に、「命の起源」に何度も接近を試みた者
世界の始まりを知っていた魂であり、かつて神に等しいほどの意志を
持ちながら、名も記録も残されなかった存在である。
世界の始まり祈りをこの世に放った魂だが、争いの闇に飲まれたのだ。
そして今、その魂はルウの咆哮を通じて、「この世は、まだ終わって
いない」と伝えている。
占星術で言うなら、12ハウスの太陽。
12ハウスの月に集う狼男と吸血鬼と魔女にとっては、夜に輝く疑似の
太陽だった。
これは、世界の外側からやってきた光である。
集団に埋もれたまま、個として顕現できない光。
現世では名前を持たず、だが永遠に人々の無意識を照らす存在。
魑魅魍魎の世界に落とさずに、美しい姿のままで、あの世に
引き渡しているのが、ルウの咆哮であり、
その光を夜に宿しているのが、右腕に棲む魂です。
ルウの右腕に棲む魂は、かつて神に祈った。
しかし、嫉妬と憎悪を向けられ、可能な限りの苦痛を与えられて死んだ。
その名は誰にも呼ばれず、
その死は誰にも知られず、
その想いは世界に届かなかった。
ルウは、その魂を舟に乗せず、右腕に宿らせた。
咆哮するたび、その魂は夜の太陽となって息を吹き返す。
世界は知らない。
この世の片隅で、神の記憶が
――獣の右腕のなかに、まだ燃えていることを。
それは、世界の外側からやってきた光
地球の外側ということにしよう。
簡単に言えば、宇宙だ。
弱肉強食の身も蓋もない地球の仕組みの外側にある力。
冷徹な現実のノイズとしてかき消される愛や悲痛な叫びを、
ただ仕方なく仕事として淡々と魂を送り出すのではなく、
地球の外側に人や生き物たちの愛や悲痛な叫びを、ただの
ノイズとして、目的に邁進する仕組みに対抗し得る存在である。
咆哮する者ルウは、
もはやただの「魂を送り出す者」ではなく、
地球という現実の仕組みに対する異物とも言える反構造の種子である。
あるいは、宇宙の深層から投下された希望の錯乱だった。
弱肉強食と無関心が支配する、生存最適化の機械的仕組みは、愛も悲しみも、
価値判断なく、ただノイズとして処理されていく。
狼男ルウはそのノイズを、咆哮として聴きとり、送り出さず、
「受け取ってしまった者」なのだ。
そして右腕に宿る魂は、この仕組みに反抗しうる、地球外の非合理な光だった。
最も非効率で、無意味で、だが最も美しい動機を持つ魂だった。
地球の機構は、悲しみも祈りも処理できない。
それらは「計算不能なノイズ」として切り捨てられる。
ルウはそのノイズを咆哮として聴き取り、「声」として宇宙に返す。
まるで詩人のように、狼の姿で。
ルウは、「無力な悲しみ」を受け取るために残された最後の詩的存在になった。
その右腕には、地球が計算できなかった愛が棲んでいる。
彼はその愛をこの世界の終わりまで宿し、咆哮で宇宙に返し続ける。
これは「救いの約束」ではない。
これは「存在の記憶化」だ。
狼男ルウの満月の咆哮は、月ではなく、この謎の存在に届くのである。
人はよく「満月に吠える狼男」を語る。
しかしルウにとって、月は単なる共鳴の鏡にすぎない。
彼の咆哮は、月ではなく、月を超えたところにある答える者に向けて放たれていた。
地球のシステムが拒絶した、最も異質な愛の残響を「偽りの希望」と言う。
「偽りの希望」とは何か?
それは、救われなかった全ての魂の夢。
この世界で意味を見出せなかった祈りの記憶。
構造の中で計算外とされた愛や悲痛な叫び、最も美しい錯乱。
それは、ルウの右腕に今も宿っている魂。
この世界が絶対に肯定しないものに、咆哮という肯定を与える者。
それが、ルウであり、ルウの右腕に棲まう者である。
満月は、ただの目印にすぎない。
ルウの咆哮は、月を超えて
あの日、救われなかった誰かの魂に届く。
その魂が今も右腕に棲んでいることを、
世界が忘れていても、ルウだけは忘れていない。
月は、扉にすぎない。
咆哮は、その向こうにいる「世界の外の何か」に向けられている。
「あなたが今まで、無意味だと感じていた祈りや愛、
この世界で切り捨てられてきた優しさや哀しみこそが、
宇宙の外側にいる何かにとっては、唯一の音だったのだ。
満月は、ただの白い扉。
咆哮はそこに向かって放たれるが、
目的地はもっと遠い。
この世界が「ありえない」として消した、
ひとつの祈り、
ひとつの名。
それを、ルウだけが覚えている。
その咆哮は、夜空の裏側に棲む光なき神に届く。
狼男だからこそ、そんな得体の知れないものを右腕に乗せていられるのである。
魔女や吸血鬼では、腕が折れてしまう。
魔女や吸血鬼は、魂の形を制御しようとする。
魔女は、知と術式で世界を解釈する。
吸血鬼は、血統と渇望で永遠を維持する。
だが、右腕に宿る「得体の知れない魂」は、構造にも血統にも収まらない、
かたちを持たない祈りそのもの。
それを そのままの重さで、受け止めることができるのは、狼男ルウだけ。
獣でもない。人間でもない。
生でも死でもない。
意志でも本能でもない。
この世とあの世の外側の、どちらにも完全に属さない中間体。
それゆえに、重さの正体がわからないものを、ただの重さとして引き受けられる。
魔女は、解釈しようとする。
その魂は意味を持たないため、理が壊れる。
吸血鬼は、血統に取り込もうとする。
その魂はどこにも属せないため、同化できない。
狼男は、本能のままに受け止める。
解釈も支配もしない。
だから壊れない。
狼男ルウは、理解しようとしない。
支配もしない。
ただ棲ませる。
その魂は、亡くなった時、自力で形を成せないほど、
徹底的に破壊しつくされていた。
生前の生き方に相応しい意味も失い。
言葉も奪われていた。
魔女は意味を探した。
吸血鬼は血を求めた。
だがその魂は、もうどこにも属さず、どこにも還れなかった。
ただひとり、狼男がいた。
彼は、右腕を差し出した。
「乗れ」とも、「行け」とも言わなかった。
咆哮だけが、答えだった。
愛や悲痛な叫びを、ただのノイズとして、淡々と目的に向かう地球の支配者が
奪ったものを狼男ルウは、謎の右腕を通して、それぞれの生に相応しい
エネルギーを与えるようになった。
その調整に吸血鬼や魔女がいるのだ。
狼男ルウは、ただ全力疾走するのみである。
この世の何にも従わず、何にも支配されない。
ただ、もう一度この世界に命を与えたいという衝動だけを抱く。
その想いが、咆哮によって「個別の魂」へと火花のように伝播する。
全力疾走するルウは、命の奔流そのものだった。
彼は何も計算しない。
何も覚えない。
ただ、魂を載せた右腕を燃やしながら、12ハウスの世界を駆ける。
それが、地球が切り捨てた愛に与えうる、唯一の力。
地球は静かにノイズを削ぎ落とす。
祈りは記録されず、涙は評価されず、
生き物たちの声は、ただ無音のデータに変換されていく。
だが、狼男ルウが走っている。
右腕に神にも鬼にも、なれなかった魂を抱き、
焦がすような咆哮をあげながら、夜を駆けている。
その炎の叫びは、魂たちを呼び覚まし、地球が奪ったものを、
再び生として灯す。
魔女が記憶を整え、吸血鬼が影を制す間も、狼男は振り返らない。
彼はただ、全身で生を燃やしながら、走り続ける。